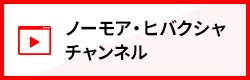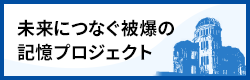10月26日、ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会の第14回「被爆者運動に学び合う学習懇談会」を開催しました。
今回のテーマは「被爆=『こころの被害』をめぐって」。会場となった立教大学・池部うろキャンパスの教室には、「非被爆者にとっての原爆という経験の意味」を学びはじめた小倉康嗣ゼミの学生を含む35人(うち被爆者8人)が、「今日はパワーポイントを使わず、じっくり議論したい」という精神科医の中澤正夫さんのお話に耳を傾け、時間を延長して熱心に議論をしました。
■ 中澤さんの問題提起=要旨=
従来、原爆被害はからだ・こころ・せいかつに3分割してとらえられてきた。それは正しかったのだろうか?――まず、こう問題を投げかけて中澤さんの報告は始まりました。
原爆がいかに人を傷つけたか、という観点から被害を分類するなら、「人とは何か」が問題になる。ヒトは高い知能を持ち、社会を形成し、一人ひとり違った「心」を持っている。過去・未来を区別し、言葉で他者と交流し、現在をそれなりの矜持をもって生きている。独自の自分と自分をとりまく環境(現存在)は一人ひとり全く違うが、「現存在であること」は同一である。
原爆は、それぞれ独自に築いてきた世界やこれからの夢も含む「現存在」を、急激に、根こそぎ破壊した。被爆者のほとんどが「一番つらいのは心の被害」というのはこの意味であり、したがって、原爆の被害はすべて「心の被害」として括ることができる。

被爆者の「こころの被害」についての記録・研究は本当に少ない。従来の被害分類では、「心の被害=精神疾患の増減、新発生」にとどまり、トラウマ論にさえいかなかった。
肥田舜太郎、千葉正子両医師らにより「ぶらぶら病」が抽出され海外にも広まっていったが、代々木病院での10年間の追跡調査によって、ぶらぶら状態は線量により誰でも呈するプロトタイプ(原型)で、「新精神障害」ではないと結論づけられた。
被爆者のおかれた状態を現存在的に分析したのはR.リフトンだ(『死の内の生命 ヒロシマの生存者』朝日新聞社、1971)。彼の功績は、死の呪縛、罪の同心円、精神的麻痺等を鍵概念として抽出し、生存被爆者が背負う悩み・痛み・苦しみを言語化・構造化したことにあるが、解決の道や未来を示唆するものではなかった。
石田忠とその門下生らが長年とりくんだ被爆者調査では、被爆者が長き漂流(逡巡)の末、原爆と対峙し、のり越えてゆく必然性を被爆者の中に見出し、反原爆の哲学(核廃絶と国家補償)へと止揚している(『反原爆―長崎被爆者の生活史』『原爆体験の思想化』)。非被爆者もまた、その後を追うことの可能性を示唆したともいえる。
私がPTSDをとり上げたのは、目に見えるからだやくらしの被害と共通の言語をもつための数量化としてであって、これでこころの被害を語るのは間違いだ。しかし、被爆体験が最悪のトラウマ、PTSDをもたらしたことは事実だ。最近、チェルノブイリの被害者たちに、フラッシュバックならぬフラッシュフォワードが起きているという報告があった。未来も希望もなく、後ろ向きの人生を送って自死に至る。3/11以後のフクシマにも見られ、広島・長崎でも同じことが起こっていたと考えられる。
■ 討議のあらまし
《「被爆者に『なる』」をめぐって》
○ 「非被爆者もその後を追う可能性」とは? 昨年、昭和女子大の文化祭で「被爆者に『なる』」がテーマとしてとりあげられたが、自分にひきつけてみると、被爆者の生き方、やってきたことから学びたいと思う。記憶にもとづく証言が可能なのは、被爆時13歳くらいまでだろう。被爆者が少なくなっていく中で、体験のとらえ方も変わっていく。一桁被爆者、胎内被爆者、2・3世、支援者…、この先どう考えていけばよいだろうか。
中澤:一番議論したかったところ。放射線の被ばく者にはなれないが、たたかっている被爆者に共感し、運動に近づけていくことはできるのではないか。
○ 被爆者の生き方を子どもたちに伝えられる教師になりたいと思って教師になった。平和教育の研究会で言われた「原爆は被害の体験で、それだけでは不十分。加害の体験も伝えなければ」に違和感をもった。一人の人間が生きていくときに、原爆を体験したことがどういうことなのかを、子どもといっしょに深く考えたいと思った。
○ 「被爆者に『なる』」を安易に使うことには批判的だ。被爆者が核兵器廃絶をなぜ求めるのか。それは原爆をのり越えたからではない。ふたたび被爆者をつくるな、という主張の背景には、今なお原爆に苦しんでいる実態がある。
原爆は様々な苦しみをもたらしたが、被爆者を突き動かしているのは、その被害のすべてではない。例えば、「あの日」の地獄の体験とは何をさしているのか。何十年経っても残っている心の傷など、人間の苦しみを本当に理解していくのは難しいが、溝を埋めていく努力をしていくしかない。
《つらい記憶と向き合い語ることの難しさ》
○ 父と兄2人が被爆。13歳だった兄は建物疎開で被爆し、25キロ離れた自宅に帰ってきた。当初3日間は興奮して話しつづけたが、その後は誰にも語らず生涯を送ってきた。その兄が、フクシマ後、80歳過ぎてから少しずつ語り始めた。自分の体験を話すようになってきたら明るくなってきた。気持ちの面で変化がおき、楽になる部分もあるのだろうか。
○ 福島ではまだ語られていない。被ばくを語ると、それだけでアウトだ。広島・長崎も語るところまでいくには、かなり時間がかかったと思う。国内外から学者らが入ってきて、語ることは非常にいい、向かい合い、言語化することが大事だと言うが、現場ではかえってマイナスが大きく、地元の人はやらない。福島は被ばくをどういう形で受けとめたらよいか、模索している。
中澤:語ることによって、フラッシュバックは必ず起きる。語ることがいかに大変か。放射線の影響ひとつとっても学者どうしが混乱し、結局、一人一人の判断に任せている状況だ。住んでいない人のいうことはあてにならず、計画してもっていったことは、ことごとく失敗している。月に1回支援に入る私は「風の人」と言われている。時々来て、地元で気づかぬ視点を出してくれる、それだけでいい。あとは余計な口はださなくていい、ということだ。
○ 7歳で被爆した私も、長いこと語れなかった。目の前で亡くなった大好きだった「おねえちゃん」(従姉)や従兄、建物疎開で引っ越すまで通っていた本川小学校でほぼ全員死亡した児童…。亡くなった人たちのことを話せなかった。被爆者であることを理由に結婚差別を受け、それを承知で結婚してくれたのが今の夫だが、子どもを産むときには悩んだ。毎晩話し合い、亡くなった人たちが私に命をさずけてくれた、と産み育てる決意をした。その後も、とても元気だった次女が癌で亡くなり、一昨年には2人の弟が相次いで亡くなった。つらいから忘れたくてしょうがなかったが、忘れられなかった。
証言するようになって35年ぐらいになる。始めから事実を語ってはいたが、だんだん自分の本当のこと(深い心の中のこと)が言えるようになったと思う。
○ 被爆者の役員のなかでも、「証言の場」では、肝心なこと、一番つらかったことは、なかなかしゃべらない。
《初めて被爆者の話を聞いた学生たちの感想から》
○ 自分たちは、忘れようと思えば忘れられるくらいのことでも、過去のいやなことに向き合うのは難しい。被爆者の体験は、忘れられない、何十年経っても逃げることができない圧倒的なものだと思った。
○ 漂流から抵抗は、原爆に打ち克ったからと思っていたが、今なお苦しんでいるからこそ、核兵器をなくしたいと思っているのだと、新たな気づきを得た。
○ 圧倒されることも多いが、若い世代がこの問題とどう関わっているのか、ゼミ活動をつうじてもっと考えていきたい。
《最後に》
○ 中澤さんは、被害を3つに分割したのは正しかったか?と言われた。運動の中では、「3つのほしょう」「(国が国家補償をすべき)3つの責任論」…といったことばが使われてきた。いずれも中身ははっきりしないが、「3つの○○」と言われると、何となく分った気になる。これは何なのかをよく考えてみてほしい。
原爆の体験は、核兵器廃絶への大きなエネルギーになってきた。しかし、二大要求のもう一つである国家補償、援護法論のなかでは、必ずしも政策化されずにきた。被爆者運動の中で、心の被害をつぐなえ、という点には重点が置かれてこなかった。それはなぜなのか。課題は解けぬまま残されている。
中澤:私には、被爆者がいなくなったら、どうやってこの世界を救えるのか、という思いがつよい。結局、人間とは何かというところに行きついてしまう。敵も人間、ヒトラーも原爆を落としたトルーマンも人間だ。今もいつ使われるか分からない状況にある。人間は、限りないすばらしさと限りない悪さをもつ、矛盾に満ちた生き物だ。
知らない人たちに、どれだけ広く伝えられるか。継承の会の役割もそこにある。